| |

これは、オレが心の中で叫んだ第一声だ。
7月25日から2日間、ニューヨーク・ブロードウエイのセント・ジェームス劇場で、ビートルズに顔も声も演奏もそっくりな4人がプレイするライブショー「レット・イット・ビー」を観た。これは2年前に日本公演も行われた「RAIN-ビートルズに捧ぐ」をさらに進化させたものだ。
ショーの幕開けを飾ったのは「アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア」。ビートルズがデビュー初期まで出演していた地元・リバプールのライブハウス「キャバーンクラブ」を模したセットでの演奏で、その姿を見て、音を聴いた瞬間、冒頭の叫び声が心の中で上がってしまった。
このライブショーは、2012年9月からロンドン・ウエストエンドのプリンス・オブ・ウェールズ劇場で上演が始まり、オレが観た前日の7月24日からブロードウエイでの一般上演が開始された。現在、英米並行のロングラン上演となっている(現在は英国でのみ上映中)。ひと足先にロンドンで観てきた関係者からは「前作(『RAIN-』)よりパワーアップしてます。曲数も30曲から約40曲に増えて10曲以上が前作で演奏していない曲です」と聞いていた。だから、それなりにレベルの向上には期待していた。
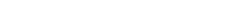
しかし、そのすり込まれた情報を持ってしてもビックラこいた。プレイヤーは複数のキャストが日替わりで出演する。オレが観た2日間もメンバーは交代していた(ジョージだけは同じ)。まずそのメンバーだが、両日ともビートルズ的な個性に溢れていた。それぞれ似ている部分は微妙に違うのだが、演奏中のギターの構え方やドラムを叩くときの仕草、歌っている時の表情やライブ中に観客に語りかける時の口ぶりなど、どれをとっても本人たちを彷彿とさせるのだ。
〝そっくり〟の迫力が違う。だからこその「やばっ!」なのだ。そのあとに続く言葉は「ひょっとしたら、かなり感動しちゃうかも!」だ。実際のところ、胸の詰まるシーンが続出した。夢を見ているようだった。
ライブは「キャバーン・クラブ」、全米に進出して出演した「エド・サリバン・ショー」、大ヒットした映画「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!」、当時の野外ライブ動員新記録(約5万5600人)を作った米ニューヨークの「シェア・スタジアム」でのライブといった流れで、その時々のお揃いのスーツ・ファッションに着替えて演奏されていき、一旦休憩が入った。この休憩前までが、ビートルズがライブ活動を行っていた時代の、いわば前半戦ということになる。
.jpg)
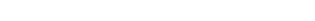
その前半部分でまず目を引いたのは「キャバーンクラブ」のセットだ。
これは、「RAIN-」にはなかった演出だ。初期のビートルズが好きなオレのようなタイプはグッとくるだろう。ここでは前作にはない「イット・ウォント・ビー・ロング」が聴ける。
それから「シェア・スタジアム」のシーンでの演出が素晴らしい。1960年代中期のテレビを思わせるモニター画面がステージの中央上の左右に取り付けられ、一方には当時のファンの熱狂ぶりを撮影したモノクロのフィルムが上映される。そして、もう一方にはいま現在、オレたちの目の前で本物そっくりの演奏を繰り広げている4人のメンバーが、やはりモノクロで映し出される。
最初は当時のライブの様子をそのまま見ているような錯覚を起こした。
次に、ビートルズの4人ではなく、ビートルズに扮した4人の映像だと気づいてからは、過去と現在が時空を超えてシンクロし、不思議な感覚に捕らわれた。あの時のビートルズを今に甦らせたステージ上の4人に〝おまえら、すげーじゃねえか!〟と快哉を叫んだ。やっぱり、こいつらは〝ヤバイ〟。このシーンでの「RAIN-」未演奏曲は「アイ・フィール・ファイン」「涙の乗車券」などだ。
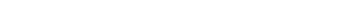
「レット・イット・ビー」を上演するセント・ジェームス劇場は、ブロードウエイの劇場街、タイムズスクエア周辺に位置し(8番街と44丁目が交わる辺り)およそ90年前に建てられている。ユル・ブリンナーとデボラ・カーが共演したハリウッド映画として知られる「王様と私」やザ・フーが発表したアルバムがミュージカル化されたロック・オペラ「トミー!」などを上演してきた歴史を持つ。客席は2階まであったと思うが、キャパは1500人程度だろう。しかし、その狭い空間が妙に心を落ちかせてくれる。床や壁に使われた木材の質感が、歴史の長さも教えてくれる。
|
|
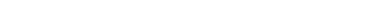
「この空間の中で、ビートルズのあの時代をゆっくり楽しもう」
劇場の雰囲気が、オレをそんな気持ちにさせたところで、いよいよ後半のライブショーが始まった。
まずは「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」に収められた作品の数々、アルバム・タイトル曲や「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」などの演奏だ。
後期ビートルズは、観客の耳をつんざく歓声に意味を見いだせず、ライブ活動を止めてしまう。代わりにスタジオ・レコーディングの際の創意工夫はどん欲を極めた。レコードの逆回転、クラシックやインド音楽へのアプローチなど、ロック・ミュージックの枠に収まりきらないアイデアの数々が輝きを放った。その第一弾が「サージェント-」だ。
光沢のあるサテン地の詰め襟の制服を模したようなコート風のジャケットとスラックス。アルバムのファッションそのままに、4人は登場した。
これは「RAIN-」の時と変わらない演出だが、アルバムでいうと、その後の「マジカル・ミステリー・ツアー」「ザ・ビートルズ(通称ホワイト・アルバム)」「アビイ・ロード」「レット・イット・ビー」のところで演奏曲目が厚みを増している。前作で未演奏の作品では「アイ・アム・ザ・ウォルラス」「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」などがあった。
.jpg)
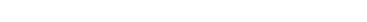
後半のステージのポイントは、当時〝演奏不可能〟といわれた曲の数々が、このライブで甦ったという点だ。後半の曲の大半は、実際にはライブで聴くことのできなかった曲だ。もしも、ジョンとジョージが生きていたら、そしてビートルズ再結成が実現していたら、こんな風に演奏してくれたのだろうか。ライブの間中、その思いが胸を去来し続けた。
そんな中、オレがどうして初期のビートルズが好きなのかを気づかせてくれる曲が演奏された。
「平和を我等に」だ。もちろん、この曲はビートルズの曲ではない。ジョンがプラスティック・オノ・バンド名義で1969年7月に発表した作品だ。ビートルズ解散のほぼ9カ月前。ジョンの気持ちがすでにビートルズから離れていた時、アメリカが引き起こしたベトナム戦争に対する反戦歌として作られ、戦争に反対する多くの若者たちの間で歌われた。「ラブ&ピース」という言葉が流行ったのもこの頃だ。
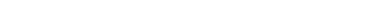
別に政治の話をしたいわけではない。「平和を我等に」を聴いて、当時のロックという音楽の精神的な部分に〝反体制〟〝反抗〟といったものが横溢していたことを思い出したのだ。ビートルズの登場は、間違いなく既成の秩序を破壊した。
アイビー・ルックが主流を占める中での長髪という見た目から始まり、コード進行にとらわれない自由奔放なメロディー・ライン、記者会見やステージでの軽口など、あの当時の若者を熱狂させた〝ロック〟という音楽の魅力を全て体現していた。あの頃、最も〝今〟を呼吸していた若者だった。オレが初期に惹かれる理由はそこなのだ。
後期のレコーディングだけの表現は、あまりにも人工的すぎて息吹きが伝わってこない。ビートルズの中で、ジョンはきっと〝今〟を感じられなくなっていたんじゃないか。それを考えると、ポールとジョンの別離を象徴するようなこの曲を、2人が同じステージに立って演奏しているような錯覚を起こさせるこのシーンは、何ともいえず奇妙で切ない場面だった。
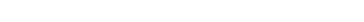
さて、終盤に「平和を我等に」から「レット・イット・ビー」へとたたみかけたライブのラストを飾ったのは、「ヘイ・ジュード」だ。ポールの来日公演では、この曲の大合唱が各公演でホールの外まで響き、みんなで歌うことの快感と高揚感を伝えていた。2012年のロンドン五輪でも、ポールがピアノでこの曲を演奏し、会場に大合唱が起きた。いわば大合唱ソングの定番だ。ブロードウエイのここセント・ジェームス劇場でも、もちろん大合唱の大団円となった。
さらに感動を増幅したのは、大合唱の興奮が収まらないうちに劇場の出入り口という出入り口がすべて開放され、歌いながら外へ出たことだ。劇場街の喧噪という現実の中に放り出され、パワーが漲るのを感じた。
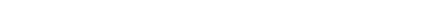
昨年は11月にポールが9年ぶりに来日公演を行なった。2014年3月、その余韻が続いているうちに「レット・イット・ビー」の日本公演が始まる。これだけ濃密にビートルズを体感できる機会は2度と訪れないだろう。
玉井 哲(たまい・あきら)
競馬新聞社、編集プロダクション勤務ののち、1986年にサンケイスポーツに入社。 88年からサンケイスポーツ文化報道部で音楽担当記者。同部次長、部長を経て、現在は編集委員。ビートルズはほぼ歌えるが、最も得意な曲は「Oh!Darling」。
一番好きな曲は「抱きしめたい」。ザ・ライターズとして「青い三角関係」というCDを出したことがある。
|
|






.jpg)
